はじめに
会社に勤めていると、毎期「目標設定」という業務を課されます。私はこれが嫌で嫌でしょうがありませんでした。なぜなら、目標設定というのは名ばかりで、実質的には自らのノルマを自分で作るというくだらない作業にしか思えなかったからです。
会社における目標設定の実態
会社での目標設定は、大きく二つに分けられます
1. 会社・業績に対する目標営業成績など、業務に直結した数値目標を設定します。しかし、ここに大きな問題があります。達成できないと評価が下がるため、無駄に高い目標を掲げることはできません。結果として、「確実に達成可能な、あってもなくても変わらない目標」が出来上がります。
2. 自己研鑽に関する目標個人として本当に達成したい目標と、会社が期待する課題は往々にしてかけ離れています。結局、業務に沿った達成可能な目標を立てざるを得ず、こちらも形骸化します。
このように、会社での目標設定は本人の能力開発や成長のためではなく、評価のための指標やノルマとして機能しているのが現状です。そうであれば、わざわざ自分で考えて設定する意味があるのでしょうか?会社がノルマとして課すのであれば、最初から会社が決めてくれた方がよほど合理的です。
個人における目標設定の意義
一方で、会社を離れた「個人の目標設定」は非常に有意義だと考えています。私は節目ごとに、自分がどの方向に進みたいか、何をやりたいかという大きな目標を立てます。これらの目標は、達成できるかどうかは別として、自分の行動を変える大きなモチベーションになります。
具体例を挙げると:
- 異業種への転職:一社目を離れて今の仕事に移るという大きな決断ができたのは、明確な目標があったから
- FIRE:次なる大きな目標として、経済的自立と仕事との向き合い方の変化を目指しています
こうした目標には、具体的なチェックポイントが伴います。例えば、異業種への転職では期間を区切って技術習得を行うことやその業界が自身に合っているかどうかを短期間で判断しなければなりません。期間というのが重要で、だらだらと行動を先延ばしにしないためには必ず設定すべきです。FIREに向けては「必要な金融資産額」「生活水準の見直し」「資産が貯まるペース」など、行動変容を伴う数値目標を設定しています。
目標管理の歴史から学ぶ
目標管理のスタートは、ドラッカーの「マネジメント・オブ・オブジェクティブス・アンド・セルフコントロール」に遡ります。目標を設定することで人は自己管理でき、目標に向かって進めるという考え方でした。OKR(1970年代)MBOの問題点(目先の目標を意識しすぎて目的を見失い作業化する)へのアンチテーゼとして誕生しました。Objectives and Key Resultsの略で、重要なのは:
- 自分がどこへ行きたいか
- 到達するためのチェックポイントをどう決めるか
この2点が、私にとって非常に共感できる考え方です。個人のモチベーションとその源泉こそが重要なのです。
日本企業の目標設定の問題点
現在の日本企業における目標設定は、評価制度と結びついているため、本来の趣旨から大きく外れています
- 高すぎる目標を掲げると達成できずに評価が下がる
- 頑張った割に報われない結果につながりがち
- 目標設定と評価制度を混ぜないのがベストだが、評価指標が必要という現実もある
理想的な働き方とは
私が最初に働いていた業界では、目標設定もノルマも存在しませんでした。それは非常に専門性が高い職業で、組織全体の要求水準が非常に高かったためです。
- 必要なことをやるのは当たり前
- 自分自身が高いモチベーションを持って努力するのが当然の文化
- 金銭的な報酬より、社会貢献や自己実現が報酬になる世界
これこそが、あるべき姿ではないでしょうか。
結論
目標設定というものは、自分の人生において非常に大切なものです。自身のモチベーションに応じて、やりたいことをやり、やりたい方向に向かって行動を変化させていくこと——これが本来の目標設定の意義です。一方で、会社における目標設定は非常に歪んだ状態にあります。時間の無駄だと感じるくらいなら、いっそやめるか、評価制度の一環として素直に「ノルマ」として課した方が誠実ではないでしょうか。大切なのは、自分がどうなりたいか、どこへ行きたいかを明確にすること。そして、そこに到達するためのチェックポイントを設定すること。会社の形骸化した目標設定に縛られることなく、自分自身の目標を大切にしていきたいと思います。






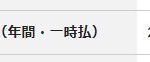
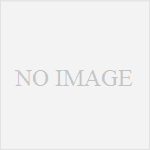

コメント